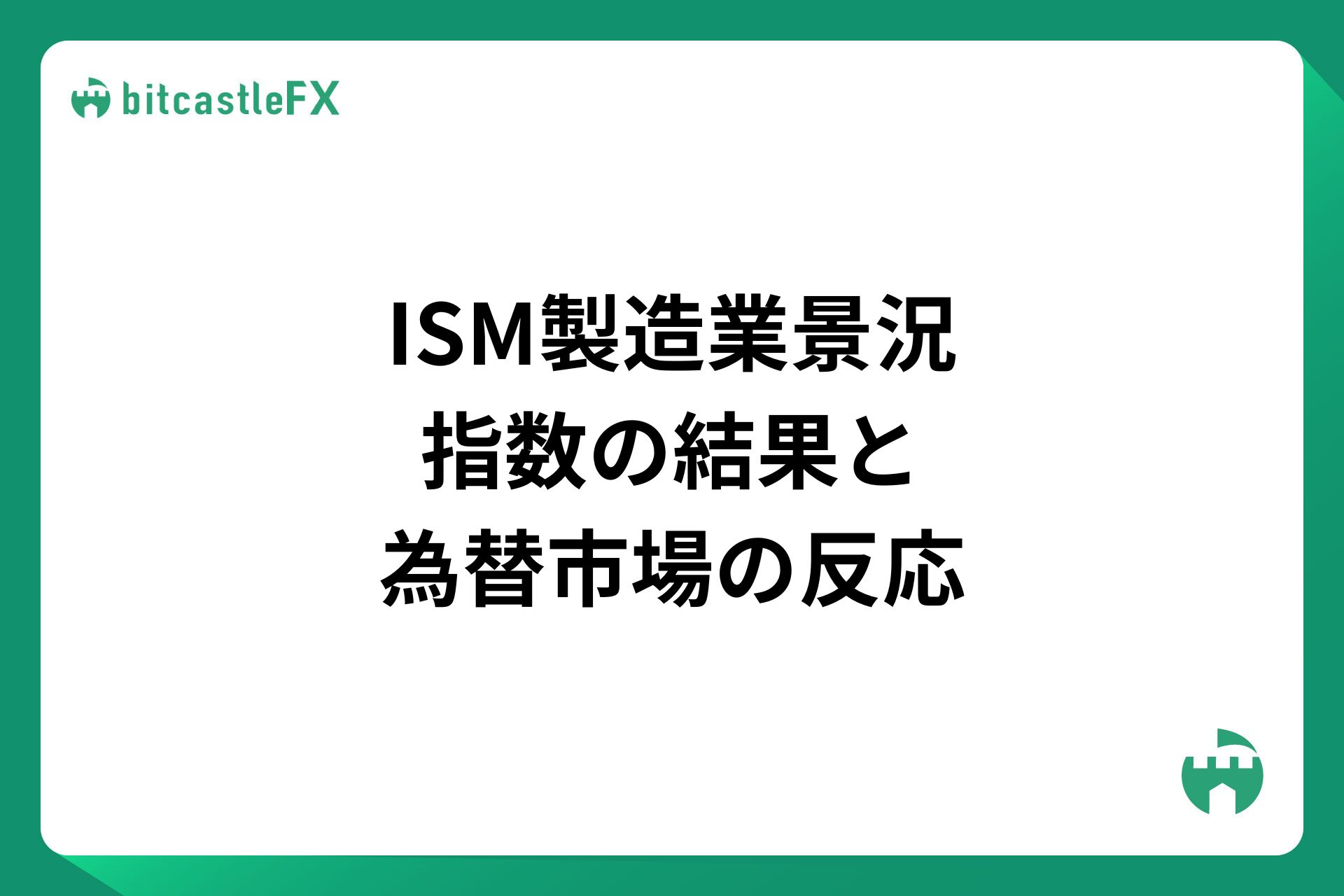米景気の先行指標として注目されるISM製造業景況指数が11月3日に発表されました。
10月の結果は市場予想を下回り、製造業の活動は再び縮小局面に。
生産や雇用の減速が続く一方、仕入価格の上昇が重しとなり、インフレの粘り強さと景気減速の両面が意識される内容となりました。
この記事では、最新のISM製造業景況指数の中身と市場の受け止め方、そして発表後の為替市場の反応(ドル円・金利など)を整理していきます。
ISM製造業景況指数の結果
10月の米国ISM製造業景況指数(PMI)は48.7%(前月49.1%から0.4ポイント低下)となり、市場予想(約49.4%)を下回る結果となりました。
これで製造業の活動は8カ月連続で縮小。
一方、総合的な米経済は66カ月連続で拡大を維持しています(参考:Manufacturing PMI® at 48.7%October 2025 ISM® Manufacturing PMI® Report)。
景況感の節目とされる「50」を下回る状況が続き、製造業部門の停滞が改めて意識される形となりました。
ISM製造業景況指数の中身
指数の内訳を見ると、
-
新規受注(New Orders):49.4%(+0.5)と小幅改善も、依然として縮小圏。
-
生産(Production):48.2%(▲2.8)と再び悪化。
-
雇用(Employment):46.0%(+0.7)で9カ月連続の縮小。
-
仕入価格(Prices):58.0%(▲3.9)で価格上昇圧力はやや緩和。
-
サプライヤー納期(Supplier Deliveries):54.2%(+1.6)とやや遅延傾向。
生産と在庫の縮小が全体指数を押し下げた一方、新規受注や受注残は若干持ち直しており、底打ちの兆しは見られるものの回復力は弱い印象です。
業種別では、食品・飲料、輸送機器が拡大した一方、繊維、化学、電子部品、機械などは引き続き低調。
調査コメントでは「顧客の発注削減」「貿易摩擦や関税政策への不透明感」が多く、需要の先行き不安が根強く残っています。
ISM製造業景況指数のポイント
今回のPMI低下は、米国内の需要鈍化と世界的な製造業の減速が重なった結果といえます。
雇用の減少ペースはやや鈍化したものの、企業は「人員削減や採用抑制」を継続しており、短期的な生産回復は見込みにくい状況。
一方で、仕入価格は上昇が続いており、コスト圧力が残る点も懸念材料です。
特に鉄鋼・アルミなど素材価格の高止まりは、利益率の圧迫要因になっています。
全体として、「製造業は依然として縮小局面、ただし悪化スピードはやや鈍化」というのが今回の特徴といえるでしょう。
ISM製造業景況指数の為替市場の反応

発表直後の為替市場では、ドル売り優勢の反応となりました。
景況感の悪化が米景気の減速懸念を強め、FRB(米連邦準備制度理事会)の早期利下げ観測が意識されたためです。
ドル円は発表直後に一時的に下押しし、米長期金利も低下。
市場では「ISMの弱さが11月の雇用統計にどう影響するか」が次の焦点となっています。
もっとも、指数が42.3%を上回っていることから、「景気全体が後退しているわけではない」との見方も根強く、ドルの下値は限定的でした。
総じて今回の結果は、米経済の減速と金融緩和への期待が交錯する内容。
為替市場では短期的なドル調整が進んだ一方、投資家の関心は「製造業の弱さが今後どこまでサービス業や雇用に波及するか」へ移りつつあります。
ISM非製造業景況指数やADP雇用統計は、11月5日に発表されます。
いまならbitcastleFX(ビットキャッスル)はお得なボーナス実施中!
特に、bitcastleFX(ビットキャッスル)で取引を始めるなら、お得なボーナスが魅力的な今がチャンス!
例えば、新規口座開設ボーナスは入金をしなくても取引クレジットがもらえるお得なボーナス。
そのため、使用感を見るためにお試しで取引したい方にはピッタリですね。
さらに、入金額に応じて大幅なボーナスクレジットがもらえて資金効率を最大化したい方にピッタリです。
新規口座開設ボーナス
bitcastleFXでは新規口座開設者を対象とした、口座開設ボーナスを実施中!
しかも、口座を開くだけで15,000円の無料クレジットがもらえるので、
お得に始めるなら今がチャンスです。

最大250万円まで150%入金ボーナス
さらに!bitcastleFX(ビットキャッスル)ではお得な入金ボーナスも実施中。
キャンペーン中にbitcastleFXの口座へ資金を入金すると、最大250万円もボーナスクレジットが受け取れます。
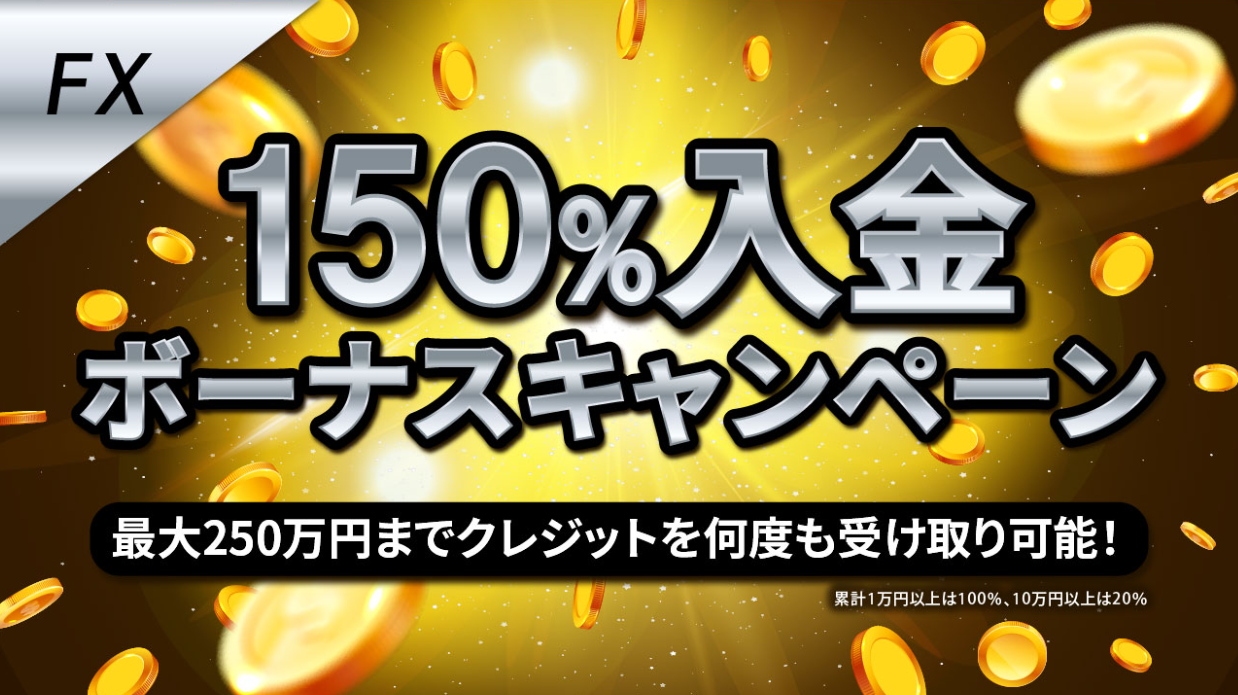
ただし、どちらのボーナスもスタンダード口座のみが対象です!
お間違いのないよう、よろしくお願いいたします。
このボーナスの詳細については、公式サイトのキャンペーンページをご確認ください。
執筆者 西村大樹